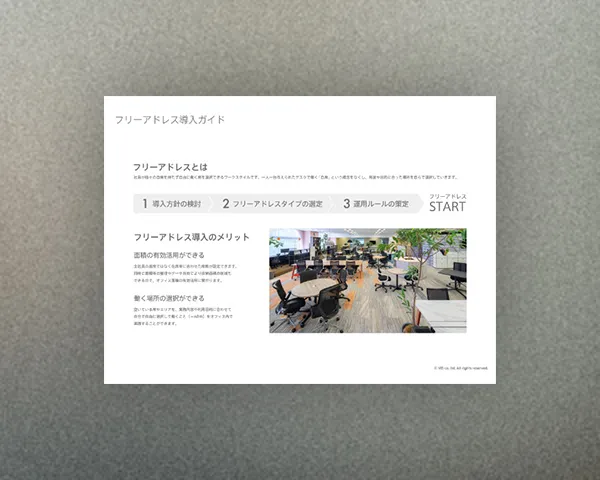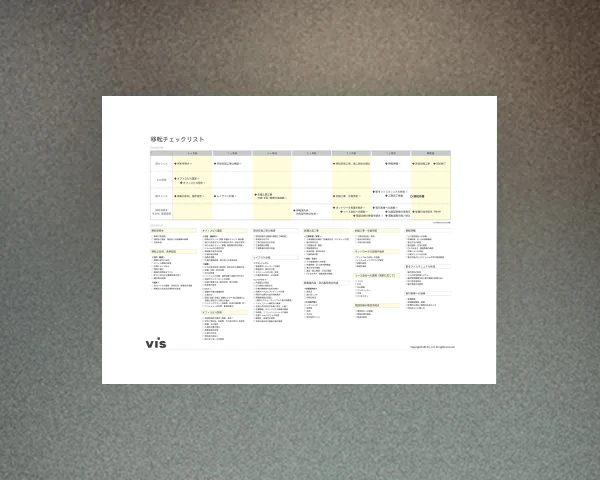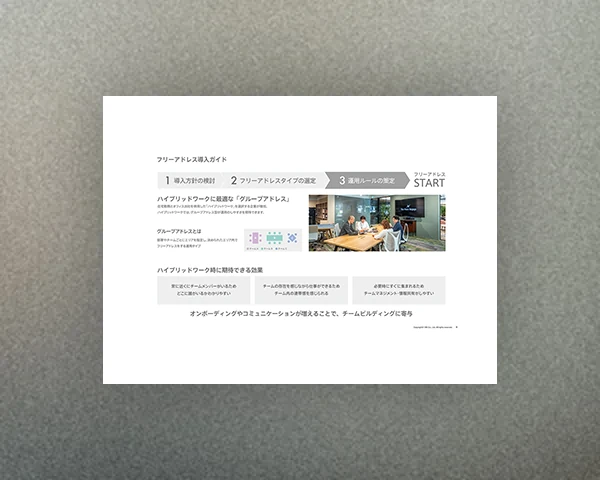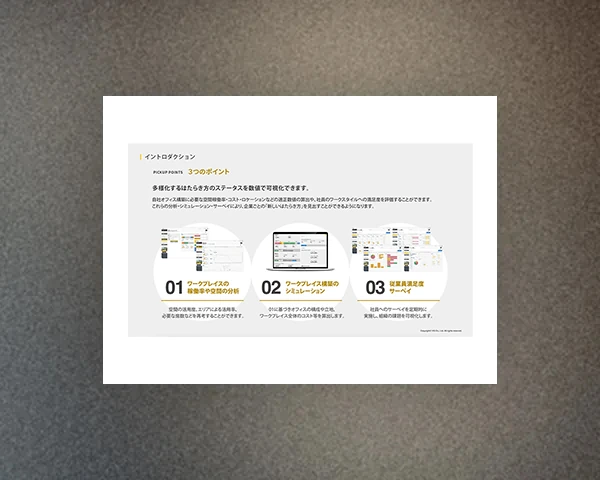「ワークエンゲージメント」を高めるために必要なものとは

今回は、「ワークエンゲージメント」と言う言葉をまだご存知でない方、
既に聞いたことはあるけれども、あまりちゃんと考えたことはないと言う方に、
是非読んでいただきたいと思っております。
まず、ここで一番伝えたいこと。
ワークエンゲージメントを考える上で一番大切なことは、
「どんなところに存在するか」よりも、「そこでどう存在する」か、であるということです。
ここではあえて、存在と言う言葉で表現しています。
(例えば社員同士で仕事と関係ない話をしている時も、その定義に含めたかったからです。)
私のプロフィールを簡単に申し上げますと、
学生時代に「働き方改革と長時間労働是正について」の卒論を書き、2018年新卒でヴィスに入社。
今は主に新規営業とプロジェクトマネージャーをしております。
今日は私が考えるワークエンゲージメント について、自分目線と会社目線からお話をして行きたいと思います。
既に聞いたことはあるけれども、あまりちゃんと考えたことはないと言う方に、
是非読んでいただきたいと思っております。
まず、ここで一番伝えたいこと。
ワークエンゲージメントを考える上で一番大切なことは、
「どんなところに存在するか」よりも、「そこでどう存在する」か、であるということです。
ここではあえて、存在と言う言葉で表現しています。
(例えば社員同士で仕事と関係ない話をしている時も、その定義に含めたかったからです。)
私のプロフィールを簡単に申し上げますと、
学生時代に「働き方改革と長時間労働是正について」の卒論を書き、2018年新卒でヴィスに入社。
今は主に新規営業とプロジェクトマネージャーをしております。
今日は私が考えるワークエンゲージメント について、自分目線と会社目線からお話をして行きたいと思います。
ワークエンゲージメントとは
そもそもワークエンゲージメントってなに?という方もいらっしゃると思いますので、
下記、サイトから引用してみました。
ワーク・エンゲージメントの提唱者は、ユトレヒト大学のシャウフェリ教授です。シャウフェリ教授はワーク・エンゲージメントを以下のように定義しています。
ワーク・エンゲージメントとは仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、以下の3つによって特徴づけられます。
・活力:傷ついてもへこたれずに立ち直る心の回復力、仕事に対する惜しみない努力、粘り強い取り組みなど。
・熱意:仕事への深い関与、仕事に対する意義や熱意、ひらめき、誇り、挑戦の気持ちなど。
・没頭:仕事に集中し夢中になることから、時間経過の速さ、仕事から離れることの難しさなど。
右記サイトより引用(参考文献:https://achievement-hrs.co.jp/ritori/?p=1628)
これを読んで私は、ワークエンゲージメントとは、
「仕事に対するポジティブな気持ちを持っている状態」なのではないかと思いました。
こんな気持ちで働けたら、会社もワーカーもみんなハッピーですよね。
下記、サイトから引用してみました。
ワーク・エンゲージメントの提唱者は、ユトレヒト大学のシャウフェリ教授です。シャウフェリ教授はワーク・エンゲージメントを以下のように定義しています。
ワーク・エンゲージメントとは仕事に関連するポジティブで充実した心理状態であり、以下の3つによって特徴づけられます。
・活力:傷ついてもへこたれずに立ち直る心の回復力、仕事に対する惜しみない努力、粘り強い取り組みなど。
・熱意:仕事への深い関与、仕事に対する意義や熱意、ひらめき、誇り、挑戦の気持ちなど。
・没頭:仕事に集中し夢中になることから、時間経過の速さ、仕事から離れることの難しさなど。
右記サイトより引用(参考文献:https://achievement-hrs.co.jp/ritori/?p=1628)
これを読んで私は、ワークエンゲージメントとは、
「仕事に対するポジティブな気持ちを持っている状態」なのではないかと思いました。
こんな気持ちで働けたら、会社もワーカーもみんなハッピーですよね。
オフィスに求めるものとは?
ここで、私がオフィスに求めることは何か考えてみました。
・気温が適切であること(暑すぎず、寒すぎず、乾燥しすぎていない空間)
・誰からも話し掛けられず、一人で集中できる環境があること
・オフィスにいることでコミュニケーションがはかどり、円滑に仕事が進められること
・座り心地の良い椅子が用意されていること
・立ちながら作業ができる環境があること
・清潔に保たれていること
・業務効率をアップして、自分の帰りたい時間に帰れるようにすること
こうして、列挙してみると、私ってとんでもなくわがままで一人よがりな欲求が多いことがわかります。笑
では、会社がオフィスに求めることは何なのでしょうか。
・仕事の話だけではなく、それ以外のコミュニケーションを通じて、お互いを知り、愛着や人との関係性を築いてほしい
・生産性の向上
・採用効率の向上
・会社のブランディング構築
・カルチャーの体現、浸透
・福利厚生の一環として社員に還元
このようなものなのではないかと思います。
これらがどちらも整った環境は、世の中にたくさんあると思います。
ただ、全て揃っているからといって「仕事に対するポジティブな気持ちを持っている状態」を生み出しているとは限らないとも思います。
オフィスができることは、
働く人の仕事に対する熱い気持ちを最大限に引き出すことなのではないかと思います。
熱意を最大化する、と言うことです。
極端な話、会社のビジョンに共感して入社した社員は、
いくら会社の環境が整っていなくても、それが離職する一番の理由にはならないと思います。
何をするか、ではなく、どうあるか、どの方向を向いて走っていくかを重視しているはずです。
・気温が適切であること(暑すぎず、寒すぎず、乾燥しすぎていない空間)
・誰からも話し掛けられず、一人で集中できる環境があること
・オフィスにいることでコミュニケーションがはかどり、円滑に仕事が進められること
・座り心地の良い椅子が用意されていること
・立ちながら作業ができる環境があること
・清潔に保たれていること
・業務効率をアップして、自分の帰りたい時間に帰れるようにすること
こうして、列挙してみると、私ってとんでもなくわがままで一人よがりな欲求が多いことがわかります。笑
では、会社がオフィスに求めることは何なのでしょうか。
・仕事の話だけではなく、それ以外のコミュニケーションを通じて、お互いを知り、愛着や人との関係性を築いてほしい
・生産性の向上
・採用効率の向上
・会社のブランディング構築
・カルチャーの体現、浸透
・福利厚生の一環として社員に還元
このようなものなのではないかと思います。
これらがどちらも整った環境は、世の中にたくさんあると思います。
ただ、全て揃っているからといって「仕事に対するポジティブな気持ちを持っている状態」を生み出しているとは限らないとも思います。
オフィスができることは、
働く人の仕事に対する熱い気持ちを最大限に引き出すことなのではないかと思います。
熱意を最大化する、と言うことです。
極端な話、会社のビジョンに共感して入社した社員は、
いくら会社の環境が整っていなくても、それが離職する一番の理由にはならないと思います。
何をするか、ではなく、どうあるか、どの方向を向いて走っていくかを重視しているはずです。
どこにいるかよりも、そこでどう存在するかが大切
冒頭の結論に戻りますが、
要するにワークエンゲージメントが高まる状態は、
自分が会社に求めることと、会社が求めることの間で良いバランスを保って働いていることだと思います。
だからこそ、どんな場所にいるかということではなく、
「そこでどう存在するか」が大切であると私は考えます。
話は少しそれますが、オフィスがある意味とは何でしょうか。
PC1台あれば働ける世の中、どこでも仕事ができますよね。
でもここでなきゃいけない、ここだからこそできる、
というようなものを感じられるからこそ、オフィスが存在し続けているのだと思います。
全員が満足できる環境をつくるのは、とっても難しい。
ではどうやって作るか、どうその人の気持ちになりきるか、
それは経営者や、社員の皆さんにある意味、「憑依」しないとわからない。
だからこそ、私自身オフィスをつくる上で、
そのオフィスでどう過ごしてもらうのか、を大切にしています。
そしてこれから先は、その先、「どう過ごすのか 」を考え抜いたオフィスを創りたいと思っております。
長くなりましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。
私の働き方改革自由研究はまだまだ続きます。
要するにワークエンゲージメントが高まる状態は、
自分が会社に求めることと、会社が求めることの間で良いバランスを保って働いていることだと思います。
だからこそ、どんな場所にいるかということではなく、
「そこでどう存在するか」が大切であると私は考えます。
話は少しそれますが、オフィスがある意味とは何でしょうか。
PC1台あれば働ける世の中、どこでも仕事ができますよね。
でもここでなきゃいけない、ここだからこそできる、
というようなものを感じられるからこそ、オフィスが存在し続けているのだと思います。
全員が満足できる環境をつくるのは、とっても難しい。
ではどうやって作るか、どうその人の気持ちになりきるか、
それは経営者や、社員の皆さんにある意味、「憑依」しないとわからない。
だからこそ、私自身オフィスをつくる上で、
そのオフィスでどう過ごしてもらうのか、を大切にしています。
そしてこれから先は、その先、「どう過ごすのか 」を考え抜いたオフィスを創りたいと思っております。
長くなりましたが、最後までお読み頂きありがとうございました。
私の働き方改革自由研究はまだまだ続きます。