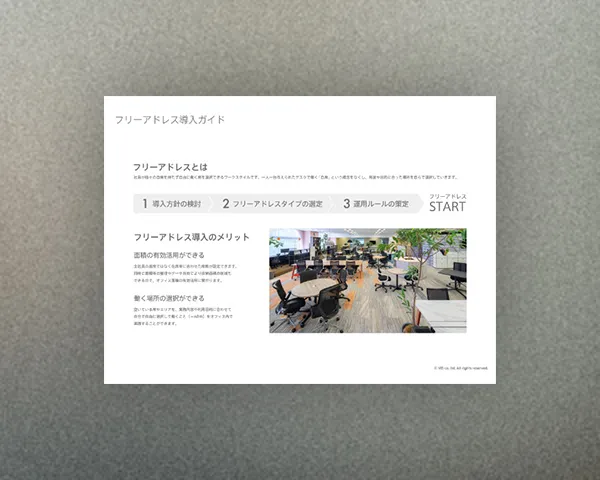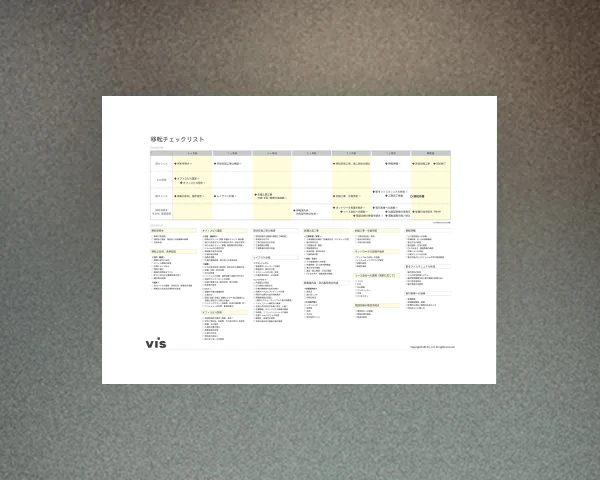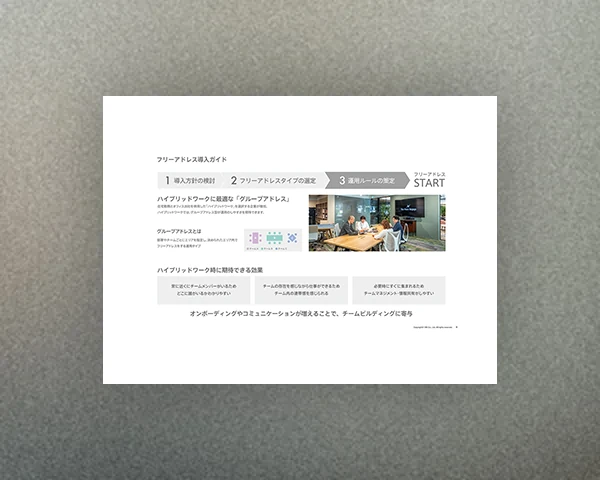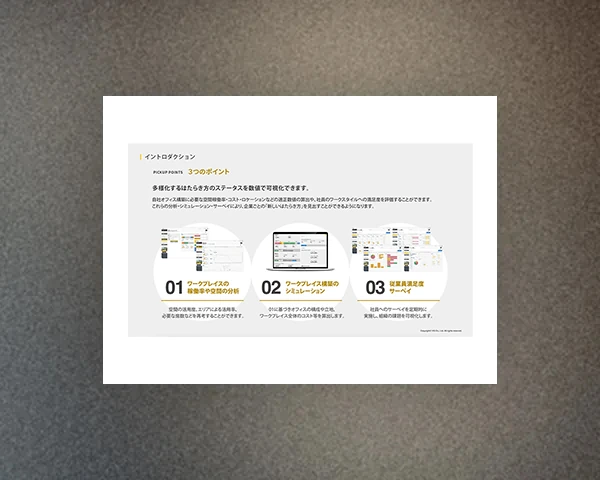イノベーションが生まれコミュニケーションが活性化するオフィス作り【vol.2/3】
2021年2月4日(木)、ヴィスが運営する新しいオフィスビル「The Place」にて「はたらく場所の必要性とこれからのオフィスのあり方」というテーマでカンファレンスを行いました。その内容を3部に分けてご紹介します。
■目次
登壇者
オフィス環境よりも人間関係が生産性に影響する
最新のオフィス作りのテーマはイノベーションが生まれるオープンな場
オープン・オフィスからプライベート・オフィスへ移行する
グリーンがあることでコミュニケーションが活性化する
おいしいコーヒーが新しい人間関係の構築につながる
フレキシブル性が高く、様々な形に対応できる「アジャイル」オフィス
vol.1、3の記事もぜひご覧ください
登壇者
オフィス環境よりも人間関係が生産性に影響する
最新のオフィス作りのテーマはイノベーションが生まれるオープンな場
オープン・オフィスからプライベート・オフィスへ移行する
グリーンがあることでコミュニケーションが活性化する
おいしいコーヒーが新しい人間関係の構築につながる
フレキシブル性が高く、様々な形に対応できる「アジャイル」オフィス
vol.1、3の記事もぜひご覧ください
登壇者
ゲストパネラー
東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域教授
日本オフィス学会 副会長 日本建築学会ワークプレイス小委員会 主査
地主広明先生
※オンラインでのご参加
パネラー
株式会社ヴィス クリエイティブ事業本部 常務取締役 大滝仁実
ナビゲーター
株式会社ヴィス デザイナーズオフィス事業本部 常務取締役 金谷智浩
東京造形大学 造形学部 デザイン学科 室内建築専攻領域教授
日本オフィス学会 副会長 日本建築学会ワークプレイス小委員会 主査
地主広明先生
※オンラインでのご参加
パネラー
株式会社ヴィス クリエイティブ事業本部 常務取締役 大滝仁実
ナビゲーター
株式会社ヴィス デザイナーズオフィス事業本部 常務取締役 金谷智浩
オフィス環境よりも人間関係が生産性に影響する
金谷:
アフターコロナにおけるオフィスの考え方には様々なものがあると思いますが、経営者の方は、オフィスを作るにあたり「生産性を上げたい」と思っていらっしゃいます。地主先生、それは学術的にみるとどのようなオフィスになりますか。
地主先生:
究極の質問なのですが、さまざまな歴史的な研究において、実は、オフィス環境が直接生産性に寄与するかというと、寄与しないという研究の方が多いのです。
一番有名なのが、1920年代のホーソン研究というもので、例えば、照明や音などが生産性にどれだけ寄与するのかを研究しました。確かに影響はするのですが、一番影響したのは「人間関係である」という結論でした。
それ以外にもさまざまな研究があり、最近であれば、Googleさんの「プロジェクト・アリストテレス」などが有名ですが、いずれも人間の問題だと結論づけています。最近では「ワークエンゲージメント」という言葉も話題ですが、これも人間の問題です。
いずれも環境や場の問題ではないとしていますが、本当にそうなのでしょうか。たしかに、ワークプレイス(オフィス)は、直接的に生産性に寄与するわけではありません。しかし、人間関係が寄与するのであれば、その人間関係を“場”が支援するということは、間接的に生産性を高めることでもあると考えられるのです。
アフターコロナにおけるオフィスの考え方には様々なものがあると思いますが、経営者の方は、オフィスを作るにあたり「生産性を上げたい」と思っていらっしゃいます。地主先生、それは学術的にみるとどのようなオフィスになりますか。
地主先生:
究極の質問なのですが、さまざまな歴史的な研究において、実は、オフィス環境が直接生産性に寄与するかというと、寄与しないという研究の方が多いのです。
一番有名なのが、1920年代のホーソン研究というもので、例えば、照明や音などが生産性にどれだけ寄与するのかを研究しました。確かに影響はするのですが、一番影響したのは「人間関係である」という結論でした。
それ以外にもさまざまな研究があり、最近であれば、Googleさんの「プロジェクト・アリストテレス」などが有名ですが、いずれも人間の問題だと結論づけています。最近では「ワークエンゲージメント」という言葉も話題ですが、これも人間の問題です。
いずれも環境や場の問題ではないとしていますが、本当にそうなのでしょうか。たしかに、ワークプレイス(オフィス)は、直接的に生産性に寄与するわけではありません。しかし、人間関係が寄与するのであれば、その人間関係を“場”が支援するということは、間接的に生産性を高めることでもあると考えられるのです。
最新のオフィス作りのテーマはイノベーションが生まれるオープンな場
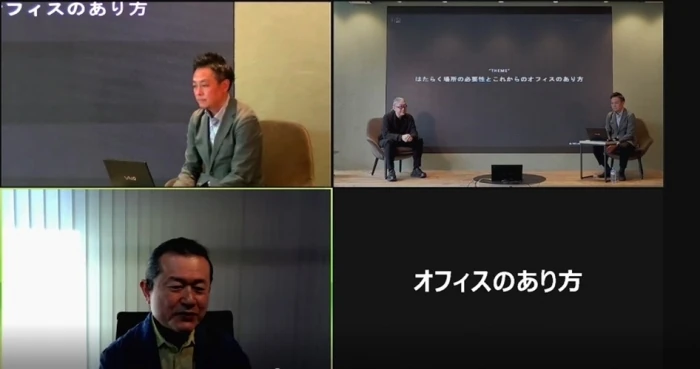
地主先生:
ここ5年くらい、多くの人がワークプレイスの目的はオープン・イノベーションだと説明しています。この場合のイノベーションは、日本的な「技術革新」というよりは、元々シュンペーターが言った「新結合」という意味です。
つまりAとBを結合させて、哲学用語でいえば、アウフヘーベン(止揚)して、上位概念に変革する、という考え方なのですが、オフィスはまさしく新結合させるオープンな場だと言えます。
それが最新のオフィス作りの肝であると世界中の専門家が言っていて、これも、話を戻せば、間接的に生産性を高めるための手法であると言えます。このイノベーション(新結合)、すなわち人と人、人とモノ、あるいはモノとモノたちをどのように出会わせるのか、結合させるのか、ということが最新の主要なオフィス作りのテーマになっていると思います。
先ほど、「センターオフィス」はハブ化してくる、つまり中間地点でしかない、分岐する地点でしかなく、分岐の先にサテライト・オフィスとか、ホーム・オフィスとか、さまざまなサービス・オフィスがあると言いました。
そのように分岐して、草の根的にオフィスが広がっていく。それが結局、知を結合させ、間接的に生産性を高めていくことになるのだろうと思います。
ここ5年くらい、多くの人がワークプレイスの目的はオープン・イノベーションだと説明しています。この場合のイノベーションは、日本的な「技術革新」というよりは、元々シュンペーターが言った「新結合」という意味です。
つまりAとBを結合させて、哲学用語でいえば、アウフヘーベン(止揚)して、上位概念に変革する、という考え方なのですが、オフィスはまさしく新結合させるオープンな場だと言えます。
それが最新のオフィス作りの肝であると世界中の専門家が言っていて、これも、話を戻せば、間接的に生産性を高めるための手法であると言えます。このイノベーション(新結合)、すなわち人と人、人とモノ、あるいはモノとモノたちをどのように出会わせるのか、結合させるのか、ということが最新の主要なオフィス作りのテーマになっていると思います。
先ほど、「センターオフィス」はハブ化してくる、つまり中間地点でしかない、分岐する地点でしかなく、分岐の先にサテライト・オフィスとか、ホーム・オフィスとか、さまざまなサービス・オフィスがあると言いました。
そのように分岐して、草の根的にオフィスが広がっていく。それが結局、知を結合させ、間接的に生産性を高めていくことになるのだろうと思います。
オープン・オフィスからプライベート・オフィスへ移行する
地主先生:
最近の先端的なオフィスの経営者たちの話を聞くと、多くの人が「オープン・オフィス」から「プライベート・オフィス」へ移行しています。つまり、今までのオフィスは組織を管理するための組織空間でした。そうではなくて、内容に応じて場所選択できるように、つまり、アクティビティのために場所を作ります。
大きなオープンスペースで人がだらだらと働くのではなくて、それぞれのスペースに明確な機能を与えて、個人のアクティビティを補完する形で場所を作りこんでいく。それによって個を高める。その高まった個が新結合することによって、上位概念が生まれて、生産性が高まっていく、という考え方だと思うのです。
だから、経営視点から考えると、そのようなビジョンを経営者が持てるか否かが、結果的に生産性を左右するのではないかと思います。
金谷:
なるほど。ありがとうございます。学術的にはオフィス環境によって生産性が高まるという報告は少ないということですが、先生がおっしゃったように、人間関係をよくするための環境づくりはデザインの課題だと思います。人間関係をよくするためのデザイン、人と人とのコミュニケーションを増やすデザイン、そういったものは確かにオフィスデザインのテーマになります。
最近の先端的なオフィスの経営者たちの話を聞くと、多くの人が「オープン・オフィス」から「プライベート・オフィス」へ移行しています。つまり、今までのオフィスは組織を管理するための組織空間でした。そうではなくて、内容に応じて場所選択できるように、つまり、アクティビティのために場所を作ります。
大きなオープンスペースで人がだらだらと働くのではなくて、それぞれのスペースに明確な機能を与えて、個人のアクティビティを補完する形で場所を作りこんでいく。それによって個を高める。その高まった個が新結合することによって、上位概念が生まれて、生産性が高まっていく、という考え方だと思うのです。
だから、経営視点から考えると、そのようなビジョンを経営者が持てるか否かが、結果的に生産性を左右するのではないかと思います。
金谷:
なるほど。ありがとうございます。学術的にはオフィス環境によって生産性が高まるという報告は少ないということですが、先生がおっしゃったように、人間関係をよくするための環境づくりはデザインの課題だと思います。人間関係をよくするためのデザイン、人と人とのコミュニケーションを増やすデザイン、そういったものは確かにオフィスデザインのテーマになります。
グリーンがあることでコミュニケーションが活性化する
金谷:
オフィス環境における具体的な仕掛けづくりについて、大滝さんはどうお考えですか。
大滝:
一つ言えることとして、コロナ禍ではグリーンを入れることが主流になってきていると思います。このビル(The Place)でも、外から見るとグラスハウスのような形になるくらいグリーンを使っていますし、当社のオフィスでも使っています。
グリーンがあることで、心が和む。自然と柔らいだ雰囲気の中で、コミュニケーションが活性化する、という効果も一つもあると思います。
金谷:
グリーンを入れることで、ストレスを軽減し、その場も明るくなる。会話も弾む。そういう効果が生まれるということですね。
大滝:
そうです。理論上、視界の中の25%をグリーンが占めるとオフィスでは一番環境がいいと言われています。そこまでの量のグリーンを入れるのは大変ですが、ある程度その数値に近づけられたら良いと思います。
オフィス環境における具体的な仕掛けづくりについて、大滝さんはどうお考えですか。
大滝:
一つ言えることとして、コロナ禍ではグリーンを入れることが主流になってきていると思います。このビル(The Place)でも、外から見るとグラスハウスのような形になるくらいグリーンを使っていますし、当社のオフィスでも使っています。
グリーンがあることで、心が和む。自然と柔らいだ雰囲気の中で、コミュニケーションが活性化する、という効果も一つもあると思います。
金谷:
グリーンを入れることで、ストレスを軽減し、その場も明るくなる。会話も弾む。そういう効果が生まれるということですね。
大滝:
そうです。理論上、視界の中の25%をグリーンが占めるとオフィスでは一番環境がいいと言われています。そこまでの量のグリーンを入れるのは大変ですが、ある程度その数値に近づけられたら良いと思います。
おいしいコーヒーが新しい人間関係の構築につながる
金谷:
それからオフィスにカフェを設けることも一つですね。カフェの機能にはコーヒーさえあればいいのです。ランチタイム後など、おなか一杯になって、コーヒーを飲みたくなる人が結構います。
おいしいコーヒーを飲めるからカフェに人が集まり、コーヒーカウンターの列に並びます。行列ができるので、普段話さない人とも挨拶をしたり、「最近どう?」みたいな会話に発展したりして、それが新しい人間関係の構築につながります。
そして、今度飲みに行こうとか、遊びに行こうよとか、その後に繋がることもあるので、そこにオフィスにカフェをつくる意味もあるのだと思います。
大滝:
そうですね。日々オフィスの中ではみんな忙しく動いているため、なかなか声をかけにくい。なので、パントリーカウンターに近づいた時を狙っているという話も聞いたことがあります。そういうきっかけの一つにもなっていると思います。
それからオフィスにカフェを設けることも一つですね。カフェの機能にはコーヒーさえあればいいのです。ランチタイム後など、おなか一杯になって、コーヒーを飲みたくなる人が結構います。
おいしいコーヒーを飲めるからカフェに人が集まり、コーヒーカウンターの列に並びます。行列ができるので、普段話さない人とも挨拶をしたり、「最近どう?」みたいな会話に発展したりして、それが新しい人間関係の構築につながります。
そして、今度飲みに行こうとか、遊びに行こうよとか、その後に繋がることもあるので、そこにオフィスにカフェをつくる意味もあるのだと思います。
大滝:
そうですね。日々オフィスの中ではみんな忙しく動いているため、なかなか声をかけにくい。なので、パントリーカウンターに近づいた時を狙っているという話も聞いたことがあります。そういうきっかけの一つにもなっていると思います。
フレキシブル性が高く、様々な形に対応できる「アジャイル」オフィス
金谷:
先ほどの地主先生のお話の中で、「オフィス環境は生産性に直接的には関与しないが、間接的には高める」とありました。私たちもオフィスデザインをする際は複合的に人と人とが交わる仕掛けづくりをしていますし、各家具メーカーさんも試行錯誤しながら、毎年新しい商品をリリースされています。
最近はやはり、人と人とが交わるということに加えアジャイルな考え方も重要になってきています。例えば家具の傾向では、動かしやすいとか、すぐに書ける、すぐにアウトプットできる、それをまとめられる、というものが増えていると思います。
これからアフターコロナに向けてオフィスを作っていく中で、どのようなオフィス作りをするべきか、企業の皆さんはどのような点に注意してオフィス作りをするべきか等、意見をいただけますか。
大滝:
やはり一つは、フレキシブル性だと思っています。この先もまだウィズコロナの状態が続いていくと思われますが、アフターコロナになったらまた状況が変わっていくでしょう。
現在日本では、政府から70%をテレワークにするよう推奨されている中で、オフィスにいる人が少なく、来社や他社への訪問も少ないという状況があります。
オフィス作りの提案をするにあたって、この先にまたどういう動きがあるか本当に読めず、世の中の変化に対応しなければならない状況です。がっちり作りこんで動かせないと、それを変えるために追加で経費が発生し、素早い変更ができなくなることが懸念されます。
什器や設備を素早く動かせる、様々な形に対応できる「アジャイル」、さらに「なくせる」「増やせる」ということが今後、少なくとも今年は重要になってくるのではないかと思います。
金谷:
そうですね。作りこんでしまうと、「間違っていた!」ということもありますしね。
大滝:
その時は、対応するしかないですけどね。社会の状況が本当に変わっていくので、「フレキシブルに」「物を床に固定させない」ということが一つキーワードとしては出てくるのではないでしょうか。
先ほどの地主先生のお話の中で、「オフィス環境は生産性に直接的には関与しないが、間接的には高める」とありました。私たちもオフィスデザインをする際は複合的に人と人とが交わる仕掛けづくりをしていますし、各家具メーカーさんも試行錯誤しながら、毎年新しい商品をリリースされています。
最近はやはり、人と人とが交わるということに加えアジャイルな考え方も重要になってきています。例えば家具の傾向では、動かしやすいとか、すぐに書ける、すぐにアウトプットできる、それをまとめられる、というものが増えていると思います。
これからアフターコロナに向けてオフィスを作っていく中で、どのようなオフィス作りをするべきか、企業の皆さんはどのような点に注意してオフィス作りをするべきか等、意見をいただけますか。
大滝:
やはり一つは、フレキシブル性だと思っています。この先もまだウィズコロナの状態が続いていくと思われますが、アフターコロナになったらまた状況が変わっていくでしょう。
現在日本では、政府から70%をテレワークにするよう推奨されている中で、オフィスにいる人が少なく、来社や他社への訪問も少ないという状況があります。
オフィス作りの提案をするにあたって、この先にまたどういう動きがあるか本当に読めず、世の中の変化に対応しなければならない状況です。がっちり作りこんで動かせないと、それを変えるために追加で経費が発生し、素早い変更ができなくなることが懸念されます。
什器や設備を素早く動かせる、様々な形に対応できる「アジャイル」、さらに「なくせる」「増やせる」ということが今後、少なくとも今年は重要になってくるのではないかと思います。
金谷:
そうですね。作りこんでしまうと、「間違っていた!」ということもありますしね。
大滝:
その時は、対応するしかないですけどね。社会の状況が本当に変わっていくので、「フレキシブルに」「物を床に固定させない」ということが一つキーワードとしては出てくるのではないでしょうか。
vol.1、3の記事もぜひご覧ください
vol.1:オフィスがハブ化し、分散する中での「働く場所」の必要性
https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1126
vol.3:「The Place」で実践する、快適で居心地良く働けるオフィス
https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1128
https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1126
vol.3:「The Place」で実践する、快適で居心地良く働けるオフィス
https://designers-office.jp/column/workstyle/page/index.php?id=1128